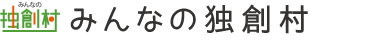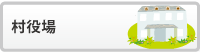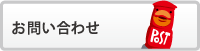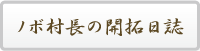寅さんとスウェーデン
映画「寅さんシリーズ」の舞台設定がスウェーデンの児童文学に由来するとはびっくりしました。そして微笑んでしまいました。才能豊かな映画監督はみんな児童文学にワクワクしたんだな~大人になっても、と思って。
寅さんシリーズに影響を与えたのはスウェーデンの女性児童文学者アストレッド・リンドグレーン作「名探偵カッレくん」という作品です。

この作家は「長靴下のピッピ」「やかまし村の子どもたち」シリーズも書いている世界的に有名な方ですが、母国スウェーデンではまた格別のようです。
というのは3年前に世界的なベストセラーとなった推理小説「ミレニアム」三部作(絶対に寝不足になる小説です!)の主役の一人にはカッレくんの名前「ブルムクヴィスト」という名前を付けてましたし、作中にもよくカッレくんが引き合いに出されてました。(さらに続編も期待されていましたが、残念ながら作家のスティーグ・ラーソンは急死してしまいました・・)
さて前置きが長くなりました。山田洋次監督の「あとがき」を引用します。
『名探偵カッレくん』を夢中になって読んだときのよろこび、まるで映画を見ているかのように行間から楽しいイメージがうかびあがったそのディテールまで、今でもまざまざと思い出すことができる。そのときぼくはすでに大学を出て駆け出しの映画人だったのだが。一九五〇年代の後半、日本映画がまだまだ娯楽の王座をしめていた時代、ぼくは松竹大船撮影所の助監督に採用され、カチンコ片手に西も東もわからず忙しいだけの毎日を送っていた。映画は一九世紀の終わりにフランスで誕生したばかり、まだ半世紀経つか経たぬかという時期ではあったが、大船撮影所の中には島津保次郎、小津安二郎、木下恵介、吉村公三郎などといった先輩たちが苦労して生み出したさまざまな映画作りのノウハウが語り伝えとしてたくさん残されていて、ぼくたち若者はその言葉を吟味しながら頭にたたきこんだものである。
その中の重要な言葉の一つに「脚本が書けなければいい監督にはなれない」あるいは「脚本の書けない監督は地獄の苦しみを味わうことになる」というのがあった。映画はまず脚本であり、監督になりたきゃ脚本を書く勉強しろ、ということである。
愚にもつかぬメロドラマやちっとも可笑しくない喜劇のスタッフとして働きながら、ぼくは懸命に映画化される見通しのない脚本を書いた。だが、オリジナルな素材というのはそうそうあるものではない。頭の中で考え出す物語はどうしても観念的になってしまい、生き生きとした人間が描けなくなる。そんな悩みにとらわれているときに読んだのが『名探偵カッレくん』だった。
いすに腰かけたカッレ少年が、虫眼鏡で仔細らしく紙切れの血痕を観察している。明るい窓の外の道路にはネコが足のうらをなめているほかは入っ子ひとり通らない静かな夏休みの昼さがり。やがて、ばたばたと足音がして親友のアンデスが汗びっしょりの顔を出す、という物語の始まり、ぼくにはたちまちイメージがうかんでくる。虫眼鏡のレンズ越しに見えるやや湾曲したカッレ少年の頁剣な表情のクローズアップ、それがこの映画のフア-ストカット。以下小説をたどるにつれて次々と映画の場面がうかんできて本をおく間も惜しいようなありさまだった。
カッレくんのあこがれの少女エーヴァ・ロッタは隣家のパン屋の愛娘。板塀は板が一枚はがれていてカッレくんはその隙間を通って彼女の家に通う、というところが妙に好きだった。後年『寅さんシリーズ』を作ることになるのだが、寅さんの実家のだんご屋の裏手に印刷工場があり、両家をさえぎる古びた板塀の一部が破れていてタコ社長はじめ工員たちは大いばりでそのあなを通ってだんご屋を訪れる、という仕組みはこの『カッレくん』からいただいたものである。
カッレくんの家は食料雑貨店、アンデスの父親は靴修理屋。彼らの親はそれぞれ家族思いの堅実でつつましい商人や職人であり、ビョルク巡査はつねに街の平和を念じ、帰る家のないあわれな酔っぱらいの世話をやくまじめな公務員である。さらにいえば、教会の神父は信者たちの幸せを祈り、酒屋はお客の健康を心配しながら酒を売り、他人の考えに耳をかたむけることのできる寛容さといたわりの気持ちを大切に生きている優しい市民がこの街の住人なのであり、都市生活とはこのようでありたいという一種のユートピアがこの物語の背景に美しく描き出されているといってもいい。
「名探偵カッレくん」をシナリオにするのにさほど時間はかからなかった。当時大船撮影所の助監督室で発行していた脚本集に投稿して掲載されたが、なんせ高橋治、大島渚、吉田喜重、篠田正浩などの錚々たるメンバーがいた時代だから少年少女向きの映画のシナリオなど関心をもたれるはずがない。数年後にプロデューサーを通してはるばるあこがれのリンドグレーンさんに映画化権の交渉をしたが、うまくいかなかった。世界的な大作家にとって、東洋の若い無名監督などいちいち相手にできないのだろうが。
ぼくは今でもこの企画に愛着がある。あれから四十年以上の歳月が経ち、老年監督といっていい年齢になっているぼくだが、実はこの歳だからこそ、少年少女が心をときめかせるような楽しい映画を作ることができるのではないか、と近頃しきりに思うのである。
二〇〇五年一月

宮崎駿さんも児童文学に大きい影響を受けているようです。彼がとても好きだというイギリスの児童文学者ロバート・ウェストール「海辺の王国」を半年くらい前に読んだんですが、これもワクワクして読めましたね。やはり子どもの頃の感性を持ち続けている人だけが「創造」のエネルギーを持ち続けられるんではないでしょうか。
投稿者:ノボ村長
Category: キラっと輝くものやこと, ほっこりすること