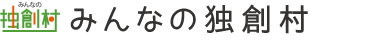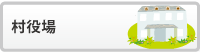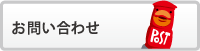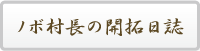SF画廊「ガス・ステーション」

エドワード・ホッパー「ガス・ステーション」(1940)
(夕暮れの店じまい)
夕方5時、この季節だとあと一時間もすれば日が暮れる。マシューは家業である給油所の店じまいをしている。
ホースに残ったガソリンを丁寧にタンクに戻した後、きつく締められていたポンプのナットを大きいスパナでゆるめてハンドルを外す。ポンプを他人が使えなくするための毎日の日課だ。
この後、事務所にしっかりと施錠し、小さな金庫を手に持ち、マシューと同じくらいに年取ったオンボロトラックに乗って十キロほど離れた自宅へ帰る。
今夜のマシューはやけにいそいそと帰り支度をしている。それにはわけがある。それは今朝、妻のモイラがマシューにかけた言葉だ。
「今日の夕食はギネスで煮込んだビーフシチューにするわよ」祖父シェーマスがアイルランドからこの地に移住して以来、マシューの家では代々この料理が一番の人気だった。アイルランドの懐かしき郷土料理だったからだ。
マシューは車を運転しながら、シチューをもう心の中で味わっていた。「俺がこの前採ったキノコもたくさん入っているに違いない。ほくほくのポテトもきっと添えてあるだろう。それにしても、先日ギネスをたくさん運んできてくれたトーマスには感謝しないとな。。。」
車を走らせて15分、マシューは自宅の煙突からおいしそうな煙がゆらゆら立ち上っているのを遠目に見て、アクセルを踏みこんだ。
(僻地のスタンド)
世界中がきな臭くなってきた1940年の今年、マシューは50歳になる。今は亡き父ショーンが始めたこの給油所を彼は継いでいる。
三つ下の女房モイラと二人だけでもう20年も営んでいる。マシューの子供たちはみな遠い町に住んでいる。彼の代でこの給油所が終わりになる可能性はとても高い。息子には必ず跡を継いでもらいたいと彼は強く思っている。
こんなちっぽけな給油所をなぜ継がせる?と思わない人はいないだろう。しかし、実はマシューがそう願うだけの大きい理由があるのだ。信じられない秘密がこの給油所にはあるのだ。。。
メイン州の東部にある森林地帯の過疎地にこの給油所はある。ここから一番近い町まで100キロ以上もある。そんな僻地には、当然ながらここしか給油所がない。そんなわけでここから先に行こうとする車は必ずここで燃料を補給することになる。事務所にはちょっとした売店もあって、飲み物や菓子類の他に、森で役に立つ道具や雑貨類も少し置いている。
給油所の前の道路は、舗装されてはいるがところどころ剥がれている。通る車がとても少ないので補修工事はいつも後回しにされているからだ。道路の奥には暗い森が奥深く拡がっている。森の中に入ると細い道路がくねくねと数十キロも走っていて、カナダとの国境につながっている。いわばルート201の裏街道というところだ。
森の中には大きな池や湖がいくつもある。祖父や父の時代には、これらの湖沼でマスなどを釣って生業を立てる漁師もいたし、ムース(ヘラジカ)や七面鳥などを獲る猟師もけっこういたらしい。彼らは森の中に小屋を建て、泊まり込みで仕事をしていた。古くからこの地に住み続けていたインディアンは彼らのガイドとなっていた。
しかし、そんな時代はもう終わっていた。今では、稀少なホワイトパインを運ぶトラック、カナダへの近道を熟知した運送屋、それと探検者きどりの連中がたまに通るだけだ。そんなわけで、森は時代に逆行してその深さを増している。
なにせ道が悪いので、馬力のあるトラックとかジープみたいな車しか通れない。ハイカラな乗用車で給油所に寄る人もたまにいるが、マシューは「あぶないから戻ってルート201を通りなさい」と強くすすめている。
(トーマスのみやげ)
トーマスはアイルランドがルーツの陽気なトラック運転手だ。月に1,2回ここを通り、そのたびにマシューの給油所に寄って燃料の補給をする。
そのときは必ず、マシューやたまに店番をしているモイラとあれこれ世間話をするのが常だった。トーマスは森の情報、マシューは都会の情報をそれぞれ必要としていたのでいつも話ははずんだ。
この前トーマスが来たのはちょうど一週間前だった。この日トーマスはみやげに「ギネス」を2ダースも持ってきてくれた。御礼にマシューは自分が採ったキノコ、モイラはお手製のブルーベリーパイをトーマスにあげた。そのギネスが今晩のビーフシチューの隠し味になっているというわけだ。
(給油所の秘密)
トーマスがギネスを持ってきた日、二人でしこたまきこしめしたせいで、マシューはいつもより饒舌だった。それでつい、マシューはこの給油所の秘密を少しだけトーマスに話してしまった。大事な秘密なのだが、あまりに荒唐無稽でトーマスは上の空だった。「幸運にも」といったところか。。。
マシューは控えめな口調でトーマスに話しはじめた。「君は、私たちがなんでこんな辺鄙なところにいるんだ?と思っているだろう」
マシューは窓に目をやり、独り言のように続けた。「実はな。。。森へ入る人たちの最後の基地という名目だが、もっと大事な理由があるんだよ。われわれケリー家に定められた使命というものかな~~~」
「へ~~~、俺は親父さんのご先祖が何かの理由でここに島流しにされたと思っていたぜ」ギネスでますます赤ら顔になったトーマスがマシューをひやかした。
「島流しか、そう言えるかもしれないな。わしのご先祖も、いやおまえのご先祖だって、故郷のジャガイモ飢饉がもとで、命からがらこの新大陸に流れてきたわけだからな~~」
マシューは続けた。「人様に話すのはこれがはじめてなんだが、おまえの先祖も同郷だから聞かせてあげよう。。。わしの祖父がアイルランドからこの地にやってきたのは、もう100年ちかくも前のことだ。コーブの港から一家いや一族、棺おけ船に乗って命からがらこの地へたどり着いたわけだ。なぜ棺おけ船っていうか知ってるか?栄養失調で乗員の半分以上も亡くなったからだよ」
マシューはパイプに火を付けながら話を続けた。「故郷を離れるのはとてつもなくつらいことだったろう。アイルランドは「緑と妖精の国」と言われてきた。ご先祖たちは食料さえ十分あれば決してその地を離れようなどとは思わなかったはずだ。それでも彼らがここアメリカの端っこに来ることを選んだのには大きな理由があった。言葉が通じることは一番だが、それと同じくらいに、故郷を思い出させる断崖の多い海岸と手つかずの豊かな森と湖があったからと言われている」
「しかし、実はもっと大きな理由があったんだよ。。。我々の祖父が移住してきたとき、一緒に連れてきたものがあるんだよ」
「ふ~~~ん、少しおもしろくなってきたな」と、トーマスはマシューをうながした。
マシューは用心深く回りを見渡してから、とてもまじめな顔をして、小声でトーマスに話した。「連れてきたのはいったい何だったと思う? それはな、アイルランドの森に住む妖精たちだったんだよ」
トーマスは思わず、飲んだばかりのギネスを口から吹き出してしまった。「なんだって!まさかそんなおとぎ話みたいなことを俺が信じるとでも思ってるのかい。ま~~ビールのつまみとしてはおもしろいけどな」
そう言ってから、彼は腕時計を見て立ち上がった。「そろそろおいとまするぜ。モイラにブルーペリーパイありがとうって伝えておいてくれ」
トーマスの年季の入ったトラックは、そろそろ薄暗くなってきた森をヘッドライトで照らし、轟音とともに黒い排気ガスを思い切り吹いて、元気よく走り出した。
(アイルランドの森で)
1846年の秋、マシューの祖父シェイモスは30代だった。前年から続くジャガイモ飢饉が、この年も島全体を襲っていた。彼は家族や村の仲間たち数十名とともに、泣く泣く愛おしいアイルランドの土地を離れることを決心した。なんとか生き延びるために。
船に乗る数週間前のことだった。何か食べるものを探そうと、祖父たち数名は森に入っていた。ところがキノコは採り尽くされ、獣も捕えることができず、もう日が暮れかかっていた。食料を待っている家族にどんなものでもいいから持ち帰りたいという思いで、なかなかあきらめきれなかった。そうしているうちにこんなに暗くなってしまったのだ。
意気消沈している祖父たちは互いに言葉をかわすこともなく、枯れ枝にボロ布を巻いたたいまつをかざし、家路へと足を向けた。ところが歩き慣れた森のはずなのに、どういうわけか彼らは道に迷ってしまった。
しばらく堂々めぐりをしていると、突然どこからともなく女の声が聞こえてきた。その声は彼らにこう語りかけた。「わたしたちはこの森の妖精です。。。遙か昔から、あなたたちと私たちは、互いに畏怖と同時に親しみも感じながら、この森でともに生きてきました。今、あなたたちはこの森を去ろうとしています。実は、あなたたちが去ると私たちは生きていけないのです。私たちは人間界と深い関わりがあるのです。私たちは人間の魂と他の動植物の魂の間に存在するからです」
しばらく沈黙があった。祖父たちはみな声を押し殺し、次の声を待っていた。やがて女の声は落ち着いた男の声となった。「あなたたちにお願いがあります。新しい地にもし森があるなら、私たちも連れて行ってもらえませんでしょうか。。。この森で過ごしてきたようにお互いがこれからも一緒に生きていけるようにできないでしょうか。。。」
祖父たちはたいまつの火で互いの表情を確かめあった。その表情はみな同じだった。安堵と慈愛、そして強い決意があらわれていた。
(旅の仲間たち)
妖精たち、いや正確には妖精や妖怪たちを、祖父たちはどのようにして新天地へと運んできたのだろうか?
祖父たちは、妖精たちを穀物の種と一緒に麻袋の中に隠したり、植木鉢の土の中に隠したり、ありとあらゆる工夫をした。妖精たちはその姿をとても小さくできたし、木の実や苔や樹液のようなものに変身することもできたから、さほど運搬の苦労もなかった。
大西洋を渡る航海は過酷だった。船は「棺おけ船」と呼ばれた。栄養失調などで乗客の半数は航海中に亡くなったからだ。しかし祖父たちがなんとか生き延びてアメリカに着けたのは、妖精たちの守りもあったからに違いない。
妖精たちを生かすために選んだ土地が、いくらかでも故郷に近い雰囲気が残るここメイン州だったというわけである。深い緑の森、いくつもの澄んだ湖があった。
メイン州の奥深い森に放たれた妖精や妖怪たちはすぐにこの地へ同化し始めた。その後彼らは森を育み、森の恵みをますます増やしていった。祖父たちとその子孫に対する永遠の感謝のしるしとして。
(緑の国)
祖父たちがメイン州に移住した1846年、偶然にも、「ウォールデン 森の生活」で有名なアメリカのロマン主義思想家ヘンリー・D・ソローがメイン州の森を旅していた。
ソローの没後、その体験記は「メインの森」という書名で出版されたが、そこにはメイン州の手つかずの森の様子が、生き生きと綴られている。
アイルランドは「緑と妖精の国」と言われてきたが、ソローはいみじくも、本の一節に「緑の国」という見出しを付けている。妖精たちが住むには絶好の場所だったことがうかがえる。以下は、その「メインの森」からの抜粋である。
緑の国
メインのきわだったところは、果てしない森の広がりだ。それを断ち切るものは予想していたよりもはるかに少ない。わずかの山火事の跡、川沿いのわずかの集落、高い山の裸の山頂、そして川と湖を除けば、あとはすべてだ。
そこは想像以上に厳しく荒々しい場所で、春にはどこもかしこも湿ってどろまみれになる、複雑に入り組んだ場所だ。実際、ここの様相はどこを見ても冷厳で荒涼としていて、それをわずかに緩和するものは、丘の上からの森の遠景と湖の眺めしかない。
湖は不思議な場所だ。光に満ちて広がり、森はそれらを飾る精妙なふち飾りにされてしまう。それらふち飾りを従えて、アメジストのような青い山があちこちにそびえる。
太古からの湖は岸辺に起こるすべての変化を超越して、今もなお洗練された魅力をたたえる。ここにある森は英国王の人工の森ではない。君主の持ち物と違って、ここに森の法律はない。ここを支配するのは自然の法だけだ。原住民はなお追い出されず、自然はなお切り開かれていない。
ここは緑の国であり、苔の生えたシルバーバーチと水気の多いカエデの国だ。地面は赤い小さなベリーの実で飾られ、湿って苔のついた岩がいたるところにばら撒かれている。これにアクセントをつけるのが、マスやサケ、シャッドやカワカマスなど、多くの魚でいっぱいの無数の湖と急流だ。
森の中には絶え間なく声が聞こえる。コガラ、アオカケス、キツツキ、ミサゴとハクトウワシの鳴き声、アビの笑うような声、ひっそりとした流れから聞こえるカモの声、そして夜にはフクロウの鳴き声とオオカミの遠吠え。夏ともなれば、白人にはオオカミよりも恐い無数の蚊とハエが群がる。これがムースとクマ、カリブーとオオカミ、そしてビーバーとインディアンの故郷なのだ。
この厳しい森の名状しがたい優しさと不滅の生命を、いったい誰が表現できるであろう。ここでは、自然は真冬であっても永遠に春のように若々しく、苔の生えた朽ちゆく樹木でさえ永遠の若さを楽しむようにみえる。そして喜びに満ちあふれた無垢な自然は、まるで静かな幼な児のように、時に聞こえる小鳥の鳴き声と小川のせせらぎ以外には音さえ立てない。
こんなところに生き、そして死に、葬られるとは、なんとすばらしいことか。ここでは人は死と墓を嗤い、永遠に生きつづける。村の墓地から連想されるあらゆる約束事などすべて忘れ、このしっとりとした永遠に縁の森に墓を作ろうなどと考えることもない。
死んで手厚く葬られたいと思う者はそうすればよい
だが私はここに留まる。
私の自然は永遠にますます若く
太古のホワイトパインが茂るなか
(ケリー家の使命)
マシューは、なぜこのような辺鄙なところで給油所を営んでいるのだろう?
実はマシューの真の仕事とは燃料販売ではないのである。マシューというより、移住した祖父シェイマスの代から、ケリー家はこの妖精の森の番人なのである。いや「秘密の番人」と言ったほうがいいだろう。
ケリー家は代々、ここで森を汚す可能性のある者から妖精たちを守っているのである。さまざまな巧妙な方法で。給油所の前の舗装が剥がれっぱなしなのも、森の中の道がわざと入り組んでいるのも、別な道を勧めるのも、すべてはその方法のひとつなのである。
さらにマシューにはもうひとつ仕事があった。それは、その後も続くアイルランドからの妖精たちの移住を、この森で受け入れるお手伝いをしていることだ。
無骨なトーマスも実はその一人なのだが、本人は手伝っていることを知らない。彼の運ぶ荷物には、やむなく故郷を離れざるを得ない妖精や妖怪たちが密かに隠されており、マシューによって森に放たれているのだった。
祖父の代から、ケリー家はその森番を世襲しているのだった。だからいつかマシューは息子のいずれかにその秘密を話し、継いでもらわねばならないのだった。文明が進みすぎる時代にあって、息子をどう説得するか、マシューにもモイラにも頭の痛いことではあったが。
どうしようもないときはトーマスに後を託そうかという思いもあって、先日、彼に秘密をさらっと話したのだが、鈍感なトーマスにはちと無理かな、とマシューは思った。残念ながら。。。
(マシュー家の夕餉)
マシューのトラックは自宅の前に着いた。「ただいま」と、マシューが玄関を開ける。オーブンストーブで料理をしていたモイラは背中を向けたままだが、いつもの快活な声で「お帰りなさい」と答える。
やがて食卓に美味しい料理が並ぶ。ギネスで煮込んだビーフシチュー、マスのムニュエル、マッシュポテトをたっぷり付け合わせたニンジン、豆、青菜のサラダ、ブルーベリー入りのパン、それと紅茶。
部屋着に着替えたマシューとモイラはテーブルにつき、十字を切ってから手を合わせてお祈りの言葉を唱えた。それが合図だったように、飼っている猫も食卓にやってくる。放し飼いをしているのだろうか?小鳥も数羽集まってきた。
やさしくゆらめくランプの光が壁に猫の影を映し出していた。その影はみるみるうちに形を変え始めた。なんと、猫の影が人の手足を持つ「小人」の形に変わったのだ。
マシューとモイラは、小人になった猫を椅子に座らせた。モイラは「ケット・シー、今日は汚さずに食べてね」と、その猫に語りかけた。
そうしているうちに、今度は小鳥たちからも手足が生えてきた。ティンカーベルのような姿に変わったのだ。モイラはティーカップを逆さにしてテーブルの上に彼女たちを座らせた。
暖炉の側にある棚に置いてあった、ひげ面でパイプをくわえたきこりの人形も、ひょいと床に飛び降り食卓にまじってきた。
まるで童話のような、なんと楽しい夕餉なのだろう。彼らはみな妖精だった。マシューの家に住み着いていたり、森からたまにやってくるのだった。
食後はストロベリーアイスのデザートを食べながら、小鳥だった妖精が小さなハープを奏ではじめた。やがて夜も更け、みな寝る支度に入った。
(マシューとモイラの秘密)
ベッドに腰掛けてズボンを脱ぎ始めたマシュー。彼のお尻から何か長いものがはみ出していた。それは尻尾のようだった。
鏡を見ながら髪を梳かしていたモイラ。彼女の夜着が背中の肩甲骨のあたりで少し盛り上がっていた。モイラはマシューに依頼する。「あなた、寝る前に私の羽を少し梳かしてくれないかしら」マシューは「ああ、いいとも」とモイラのほうへ向かった。
メインの森は眠りにつく。眠れぬフクロウや鳥や動物たちの声がときおり遠く聞こえてくる。よく耳を澄ますと、その中に、なにか心地よい音楽のような旋律が混じっていた。マシューとモイラはその旋律を聴いて、毎夜おだやかな眠りに落ちるのであった。
(ハーンの手紙)
マシューの父ショーンには、マサチューセッツ州にアイルランドルーツの親しい友人がいた。今から40年以上も前の1900年頃、やはりアイルランドにルーツを持ち、アメリカから日本に渡り日本人となったラフカディオ・ハーンがいた。1904年、54歳で彼は亡くなるのだが、晩年、ハーンはそのマサチューセッツ州の友人にこんな手紙を送っていた。
何が人生に希望を抱かせて
くれたのでしょうか…
幽霊です
その一部は神とも呼ばれ
また悪魔 天使とも
呼ばれていました…
彼らこそが人のために
この世の有様を
変えてくれたのです
彼らこそが人に勇気と目的を
与えていたのです
自然への畏敬を教え
それはやがて愛に変わった…
彼らこそが万物を見えざる
生命の感覚と活動とで
満たしていた…
彼らこそ恐怖と美を
造り上げていたのです
もはや幽霊も天使も
悪魔も神々もいません
全て死に絶えてしまいました
電気と蒸気と数字の世界は
虚しくからっぽですラフカディオ・ハーン
ハーンの突然の死で、マサチューセッツ州の友人も、マシューの父ショーンも、メインの森で生き続ける故郷の妖精の話をハーンに聞かせる機会を永久に失ってしまった。それがとても残念だったと、ショーンは晩年マシューに話していた。
しかし、ショーンは自分たち一族が妖精と混血し、血統を守り続けているという事実は、たとえハーンに対してさえも秘密にした違いない。。。
(参考)
ヘンリー・Ⅾ・ソロー「メインの森」
大出健 訳 (冬樹社)
・・・・・・・・
小泉八雲・アイルランド幻影
~佐野史郎の「怪談」紀行~
2000年 NHK bs
→ノボショート・ショート
Category: おもしろいこと, キラっと輝くものやこと, 思いがけないこと