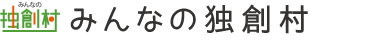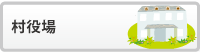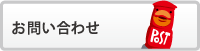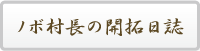超ブンカ系の数学論
数学赤点男が思い切ったタイトルを付けてしまいました。。。しかしこの歳になって知る驚愕の事実。数学の起源が言語であったとは!
(何を血迷ったか!?今日のブログ。。。)
つい最近まで「数学」とは、生命とか人間とか歴史とか文学とか、つまり私のような「超ブンカ系」にはまったく無縁の超抽象、超難解、超無機的学問であると思っていました。
超難解なスウガク理論は大天才たちの頭の中で「創られたもの」と思っていました。
と同時に(実にブンカ系的な)変な疑問がずっとわだかまっていました。
どうして机の上で行う数学(その延長上の物理学や天文学)で、何十億年も前の宇宙の様子やら果てしなき宇宙の構造やらを知る(推定?)ことができるんだろうと。
まるでウィルスが地球の全体構造を知るようなものです。
・・・・・・・・
数年前、哲学的・思弁的傾向の作品で著名なポーランドのSF作家「スタニスワフ・レム」にはまっていましたが、彼のある作品を読んでハッとさせられました。
この文章で私は(はなはだ突飛な表現ながら)「数学の母胎は私自身である」と確信したのです。
スタニスワフ・レム「天の声」より
ことばにたいする関心を私のことに戻すことにする。ここでいえることは、ことばが生まれかけた瞬間から、現実は己の秩序をそのことばに注入しはじめたということだけだ。数学は自分が発見されるまで ーだが発明されるまでではないーあらゆることばの中で眠っているのだ。
数学の花冠であるものを、根であるものから切り離すわけにはいかない。というのは、三百年とか八百年という文明の歴史の流れの中ではなく、三千年にわたる言語の進化の中で、つまり、人間関係や言語間の環境と人間との闘争の場で数学は生まれてきたからだ。
言語がわれわれのだれの知性よりすぐれていることは、生命過程を詳細にすべて自覚している肉体そのもののほうが、それについてのわれわれの認識よりはるかにすぐれているのとまったく同じである。このふたつの進化の遺産ー生命の物質と言語の情報物質ーのどちらもまだ使い切ることができないでいるというのに、われわれはすでに、それらのふたつの限界を越えることを夢みている。
ことばはつまらない屁理屈をならべることもできるかもしれない。しかしだからといって、言語が数学の概念の起源であり、つまりその概念が生まれてきたのは誤算からでも頭の回転が早かったからでもないとする私の論拠がそこにあるわけではない。
彼独特のとても読みづらい(しかし、とてもはまっていく)文章ですが、私にとって驚くべきことが書かれていました。
「言葉の中にすべてが内在している」
「数学の起源は言葉である」
「言葉は人間のあらゆる歴史の中で進化してきた」
「数学は発明ではなく、言葉にすでに内在していることの発見である」
・・・・・・・・
つまり、もともと私たちの言葉(肉体)に全宇宙の構造(森羅万象)が内在しているから、机の上でも大宇宙のことを理解できるのだ。
さらに数学は「人間学」ともいえる。数学の起源である「言葉」は人類のあらゆる行動、歴史によって進化してきたのだから。
ここから、あらゆることを(永遠に近いいつか)数学で表現することができるはず。
こんなふうに解釈できるかな〜と思います。(試論私論ですのであしからず・・・)
・・・・・・・・
小学校のとき原子模型をはじめて見て、だれもが太陽系とそっくりだと思ったはずです。
湯川秀樹博士の本を読んでみても、極微な素粒子の世界と極大な宇宙の相似性を感じているような文章によく出合います。
もともと相似物が内在するので、スケールが異なり五感を使えないことでも考えることができるのではないかと思うのです。
・・・・・・・・
昨年読んだ中沢新一さんの『野性の科学』で、数学が最も原初的な人間学であることの確信を深めました。
章のタイトルでまずびっくりです。「数学と農業」ですよ!
著者はこの章で数学の発生地点をさがしています。
それは言語の発生とともにあり、人類の言語が獲得した「喩(ゆ)」の機能に拠っていると著者は語っています。
中沢新一『野性の科学』
「第1章 数学と農業」より
この裏には、対象を指示する機能と、別々の対象を重ね合わせて新しい意味を発生させることのできる喩(ゆ)の機能が、一体になって組み込まれています。私の考えでは、現生人類以前の人類にはすでに指示機能をそなえた言語が発達しており、そこに新しく生まれた喩の機能が組み込まれて、現生人類の言語ができたと思われます。ニューロンの間に横断的な結合が生まれるよう進化が実現された結果、現生人類は重ね合わせから新しい意味を発生させる喩(ゆ)の能力を身につけるようになったことが考えられます。そしてこうして獲得された言語を使って、現生人類は無限の文をつくり、理解できるようになったわけです。
このような言語と数が、現生人類の心に同時に生まれたということには、深い意味があります。数は言語によって言い表されます。そしてその言語は、たんに心の外にある対象を指示するだけでなく、喩の機能によってたえまなく別の階層やカテゴリーにある意味どうしをループでつないで、その重ね合わせから自由に新しい意味を発生させる能力を備えています。数学はそのような意味では、数の学問であると同時に、言語のプライマルな構造と能力から、生命を汲み取ってきている学問であるということになるでしょう。数学は現生人類の心の構造に深く根ざした、根本的な学問です。そのため数学の基礎を探っていくと、現生人類の心の土台に触れることになるわけです。
(対話者:たしかに現代の数学基礎論が探求しているのは、まさにその言語と数の結びつきが意味するものです。生成文法理論などが言語の側から探求してきたのは、新しい文を生成できる言語の能力と無限に加算を続けることのできる数を数える能力との結びつきでした。どうやら鍵は、言語能力の土台をなしている喩を生み出す心の働きにあるようですね。)
同じことが音楽にも起こります。言い忘れましたが、言語と数と音楽は、現生人類の出現をまってはじめてこの世界にあらわれたものですが、それというのも音楽が一オクターブ違う倍音を同じ音だと認識する能力が、もとになっているからです。基音から五度ないし三度ずれた音に快感を感じるのも、この同じ音を認識する音楽的な喩の能力がもとになっています。まさにピタゴラスが見抜いていたように、数と音階の間には深いつながりがあります。ピタゴラスはそれを「宇宙的なつながり」と言いましたが、私たちはもっと控えめに現生人類だけに通用する「認知論的なつながり」と言うにとどめておくべきでしょう。
こういうことが、現代数学でふたたび大きな問題としてとりあげられるようになったのです。数学の全体系がそれにもとづいて構築されている数と論理には、思考の内奥で、言語に内蔵されている喩の構造が深くからみついて、数とそれを用いた論理そのものが、あの喩的ななりたちをした「不思議な環」の構造をつくつているのではないか。しかもその環は、脳内の自然過程に直結しているわけですから、数や論理を自然過程に触れさせているものでもある、ということになります。
・・・・・・・・
さらに、中沢新一さんの思想の原点となったレヴィ=ストロース『野性の思考』を読み、文化人類学が数学でもあることを知ったのでした。
実はかなりハードな本なので、一日せいぜい2-3ページしか読めず(それも時々)、読書の途中であります。今年中には読み終えることができるでしょう。
レヴィ=ストロースが未開民族の神話に発見した「構造」(私たちの原初的意識構造でもある)は次の公式で表されるそうです。
これを中沢新一さんが『野性の科学』のなかで、ダダイズムの頃の帽子の流行を例にとり説明してくれました。
その具体的な事例において、この公式は次のように展開されるそうです。
この帽子と、数式の意味について興味ある方はこちらでお読みください。
・・・・・・・・
科学のエッセンスである数学は、言語から生まれた人間学でもあります。
従来「科学の進歩は善である」と誰も疑わず、科学者は免罪符を持っているかのようにみなされてきました。
今、再考すべきなにかを私は感じるのです。
私たちの肉体にすべてが既にあり、それこそが解き明かしていくべき神秘の泉であるなら、あらゆる発見や発明は私たちの肉体にとってどのような価値があるのか、その具体化は私たちを損なう可能性はないのか、これらこそが進歩の目的であるという自然な倫理感が発生すると思うのです。
そうすると科学者は論理演算記憶能力よりも、今までまったく別な分野と考えていた文科系的というか哲学的な思考がもっとも要求されることになると思います。
原子力の発見そして原爆、その延長上にあるともいえる原発、これらの貢献と惨禍を体験した科学者というより科学技術者は、心ある人物であればだれでもが今感じているはずだと思うのです。
人類の持つ「傲慢」が引き起こしたことは何か、人類の持つべき「謙虚」とは何か、について。
スタニワフ・レム最後の長編『大失敗』は、そのことををテーマにした実に壮大で深遠な作品でした。
以上、超ブンカ系男の勝手で未熟な解釈かもしれませんが、数学(=科学)を考える(小さな)参考の一つになれば幸いです。
Category: キラっと輝くものやこと, 思いがけないこと