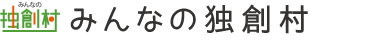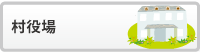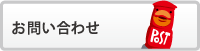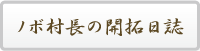妄想社会小説「一生学校の国」
妄想社会小説「一生学校の国」
イッシン政権は案の定一年しか持たなかった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
彼らの基本ポリシーは「現状の豊かさを維持するために」ということだった。
現状維持が実はとても困難であり、それをなすためには、世界との競争力を飛躍的に高めるしかない。
そのために、あらゆる場面に競争のしくみをつくり、競争を損なう政治や社会システムの無理・ムラ・無駄を徹底的に取り除く。
なかでも教育を産業に直結させ、競争力ある人材を早い段階から計画的に育成していく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
憲法は変えられ、政治的には極右傾向が顕著になり、社会価値は競争とその指標である「富=金=幸せ」の風潮がさらに強まった。
格差はますます広がり、社会は不安定さをかえって増すことになった。
競争力ある人材というのは産業ロボット化し、人間的モラルの不足が顕著になり、相対的な効率や金をますます求めていった。
中国やベトナム、インド、ブラジルなども同様の社会となっていた。
果てしない相対的な世界競争、何か軍拡と似ている様相となっていた。
今では多くの国のリーダーが公然と言う。
「ヒトラーを見習え!あの疲弊したワイマール共和国をあれほど短い期間で立て直し、世界征服さえなそうとしたのだ。その力を見直すべきだ!」
国民もこう言う「こちらのヒトラーよりあちらのヒトラーのほうが強力のようだぜ!今のリーダーはもう引きづりおろせ!」
まるで政治はデスマッチのリングさながらで、リーダーというのはグラディエーターみたい剣闘士や、強力レスラーの如きと思っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そんなイッシン政権も偶然一つ、思いもかけぬ未来の種子を蒔いていた。
彼らの時代に日本は「道州制」になり、その後、国との力関係も対等に近いほどになっていった。
イッシン政権が倒れて5年後、ある「州」の一部が「独立州」を宣言した。
新しい社会に挑戦しようとして、ネットで集まった人々の小さな集落なのだが。
その集落が属していた州の首長は(めずらしく)先進的な人で、この社会のありように限界を感じていた。
そこで、この小さな州を「本来の州の中の(擬似的)州」として、実験的に自由裁量を許したのだった。
もちろん、その頃やはり限界を感じていた多くの人々の民意も踏まえてのことだが。
その民意とは「もっと小さな単位で、顔の見える範囲で暮らしたい。昔の町や村のように」という感情的なものだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その集落が「独立州」になると聞いて、ネットを通してユニークな人々、(本当の意味で)優秀な人々が多数移住、または住民登録をはじめた。
あっというまに人口は数万人規模となった。
その州は「New吉里吉里国」と名付けられた。(彼らは「国」という名前にこだわった)
州知事には「哲学者」が選ばれた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その州は、その後の日本、いや世界の「新しい生活」のモデルとなった。
それは「新しき人の希望」プロジェクトとして全世界の教養ある人々から注目され、協力してもらえることとなった。
州民が行ったユニークなしくみを一つだけ紹介しよう。
それは、「一生学校の国」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一生学校、そんなのいやだ! 勉強なんて勘弁してくれ!
そうではない、勉強するのではないのだ。
学校は同じ学年、同じクラスに居続けることはできない、ということを応用した社会システムなのだ。
「New吉里吉里国」は、「住民は同じ会社に最長10年以上勤め続けることはできない」という法律を作った。
10年経ったらどうするか? 人は起業しなければならない。
そのために勤めている10年の間、雇用企業も「起業基金」を個人毎に積み立てる義務がある。
雇用起業は個人の起業に、「起業基金」以外にも取引先などあらゆる面で協力をしていく義務がある。
各企業の価値は、各年度の利益ではなく、どれくらい独立を助け、どれくらいそれらの(子どもとしての)企業を育てているかということで計られる。
そのような企業は信用があり、住民はその企業から物を買い、行政においてもあらゆる優遇策を受けられ、ますます安定していく。
退職した個人が起業ができない場合は別な会社に勤める。
2回目以降は最長5年間しか働けない。
その結果、人々は今食べるためにだけではなく、独立するために一生懸命職場で学ぶことになった。
勤め先が少なくて、若者が困ることもなくなった。
多様なニュービジネスが日々開花している。
この「New吉里吉里国」のユニークな商品群は今や世界ブランドとなっている。
「バチカンよりも小さく、アメリカよりも大きな国」と言われている。
by NOBO