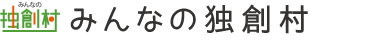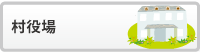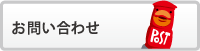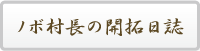ファーブル・プロジェクト
二週間ほど前、コガタスズメバチの巣らしきものを庇に発見しました。一輪挿しの素焼きの花瓶を逆さにしたようなきれいな形をしておりました。ありがたいことに蜂はこの巣を放棄していたようなので、箒の柄をつかって取り除きました。そこで思いつきました。脳トレのため昆虫をテーマにSFを書いてみようと。やっとこさ(少々長い)ショートSFを書き終わりました。
ショートSF
ファーブル・プロジェクト
1.ファーブル・プロジェクト
改良技術だけに長けた「エンジニア国家日本」で、このような奇抜な研究が国家プロジェクトとして密かに行われていたとは、いったい誰が想像しえただろう。
私がその秘密計画を知ることになったのは、私自身がその計画の中枢に組み込まれてしまったからだ。決して私が望んだのではない。有無を言わさずに連れてこられたのだ。
私はある国立大学に付属する新素材研究所の教授をしていたのだが、2050年の年明け早々、政府機関直属の某研究所に出向するようにと指示された。それも一週間以内に単身で、場所は秘密、仕事の内容も着任後に知らせるということだった。
まるで拉致されるようにして、数人の目つきの鋭い官吏とともにプライベートジェットで、(たぶん)太平洋にある日本領土の最も遠いある島に運ばれた。
数時間の飛行の後、プライベートジェットはその島にある巨大な洞窟の入り口から進入し、トンネルのような滑走路に着陸した。
研究施設もその洞窟内につくられていた。私はこの光景をどこかで見たことがあるような気がして、何かしら懐かしい気持ちがわいてきた。
既視感があったのは、きっと古典的なSF映画や、今の時代でも人気のある「サンダーバード」の映像を無意識に思い出したからだと思う。この施設をつくった人たちも、きっとこれらの作品に何かしら影響を受けていたに違いない。
2.洞窟都市の秘密会議
洞窟を入り口にして地下につくられた研究施設は、巨大なショッピングモールのような広さで、白色を基調とした機能的かつ開放的な雰囲気であった。
施設の中央には幅20メートルの通路が走り、カフェやジムなどもあって、数十人の男女がカジュアルな服装で屈託なさそうに自由に行き来していた。
大学生くらいから30代前半くらいの若い人が半分以上を占めており、まもなく還暦の私などは、ここでは長老とでも呼ばれかねないな、などと冗談まじりに思った。
私は、護衛の官吏とともに、特別らしい奥の一室へと足早に案内された。そこで私は大変な秘密を知ったが、はたしてそれが私の研究生活の総決算として喜ぶべきものかどうか、大いに迷うことにもなったのである。
応接室では三人の男女が私を待っていた。
上品でシンプルな紺のスーツを着た中年の精悍な男性は政府関係の人間らしい。名刺には「ファーブル・プロジェクト総括リーダー(略称FPR)坂本龍三」とあった。
メガネをかけた小太りの五十代の女性は化粧っ気もあまりなく、研究一筋のような人だった。名刺には「ファーブル・プロジェクト 生体応用グループ・マネジャー(略称FSM)三谷かよ子」とあった。
三人目は大学生くらいの若い男性、ジーパンにセーターという、いかにもIT産業のリーダーっぽい格好でほほえんでいた。名刺には「ファーブル・プロジェクト AIグループ・マネジャー(略称FAM)スティーブ・真田」とあった。
三人と握手の後、皆がソファーに座りいよいよ本題に入った。
まず坂本が私にお詫びをした。「川上さん、大変不躾なお誘いを致しましてまことに申しわけありませんでした。これも緊急性と秘密性がとても高い国家プロジェクトゆえ、なにとぞご容赦のほど。。。」
たしかに私はこれまでの経緯を不快に感じていたが、秘密というものへの好奇心と、この施設の思いがけぬ開放的な雰囲気で、気持ちも少し癒えていたので、素直に「はい」と答えた。
坂本が続けた。「端的に話しましょう。このプロジェクトは人類のサバイバル作戦です。人類が少なくともあと数千年生き延びるための人体人工進化を具体化するものです」
自分でも信じられないのだが、このとき私はあまりびっくりしなかった。研究生活を続けているうちに、いつかそんなことがあり得るはずと、心のかたすみで思っていたからだ。
三谷女史が少しせっかちな口調で話を引き継いだ。「人工的人体進化とは、人類に昆虫の生理や生態を応用して生存能力を飛躍的に高めることです」
私は思わず聞き返した。「それは人類昆虫化計画ということですか?」
三谷女史は苦笑しながらこう答えた。「その名称だとだれでも引いてしまいますね。しかし当たらずとも遠からずでしょう。しかしご存じのように、人類の細胞にはウイルスや、あるいは地球外生命体かもしれないミトコンドリアが共生しているということは周知の事実です。私たちはかつて異種生物と合体した先祖と同じことをすべき時が来たと思っているのです。手遅れになる前に」
3.ホモ・ハイブリダス
一番若いスティーブ・真田が、真に優秀な人物の特徴である柔和な微笑みと落ち着いた声で話に入ってきた。「私は情報工学と量子生物学、遺伝子工学を学んできました。量子レベルで考えると、様々な生物いや無機物との間にさえ根本的な差異というのはありません。生物同士が融合するのはあって当たり前のことで、進化とはそのようなものともいえます。私が懸念するのは、有機体と無機体つまり人間と機械の合体の方です」
すでに世界では、人間とマシンそしてAIが合体する「ホモ・サイエンス計画」がスタートしていたが、生体の拒絶反応をはじめとする技術上の難問、多くの人々の感情的忌避感、能力格差分断社会への不安などで頓挫している状況であった。何よりもホモ・サイエンスは遺伝できず、一代限りのサイボーグにしか過ぎないという根本的問題があった。
私はスティーブ・真田に聞き返した。「それで、あなたはここで何をしようとしているのですか?」
彼は少し考えてからゆっくりと答えた。「異なる生物種の遺伝的融合を突然変異や自然淘汰ではなく、遺伝子操作で人工的に行おうとしています。それをAIによるシミュレーションで具体化しようとしています」
私はこの短いやりとりで、プロジェクトの中身をほとんど理解した。このプロジェクトは、「ホモ・サイエンス」というサイボーグではなく、「ホモ・ハイブリダス」という新生命体(新人類)をつくろうとしているのだ。
4.デザイナーベビーの失敗
2000年代始めから2020年代に大きく進展したES細胞、iPS細胞、クリスパーCASなどを用いた遺伝子操作は、ついに禁断の聖地に踏みいった。2030年代に中国でデザイナーベビーが誕生したのだ。
キリスト教の影響が強い欧米は、人間の生殖細胞を遺伝子操作することを禁止してきたが、宗教倫理の制約が希薄な中国では、難病の根本的克服という名目で、優秀な人間をつくるための遺伝子操作を国家的プロジェクトとして進めてきた。
ところが数年後、思わぬ副作用がデザイナーベビーに生じたのである。それはある遺伝子を組み換えたところ、産まれた子供に原因不明の新たな病気が発生してしまったのだ。結局、5人のデザイナーベビーのうち二人が五歳になる前に亡くなってしまった。
国際世論はおぞましい人体実験をしたとして、中国をナチスのごとく批判し、その後人間の生殖細胞に対する遺伝子操作は、数種類のきわめて重篤な遺伝的疾患に限ってしか実施できないこととなった。
しかしこの時代、もうそんな悠長なことを言えない状況となっていたのだ。人類が科学技術の進歩という大義名分のもと、後先考えず行ってきたことが、致命的な地球環境変化をもたらしつつあった。
様々なアレルギーや原因不明の難病が数多く発生し、もう既存の医療や技術では対処が困難になってきていた。
人類の命運をかけ、新たな革命的克服方法を求めて、このファーブル・プロジェクトは発足し、禁断の扉を秘密にこじ開けようとしていたのであった。
5.ガンマキチン基質
「いったいここで私はどのような役割を期待されているのでしょうか?」私は責任者の坂本に聞いた。
坂本は答えた。「私たちの今までの研究により、今後数千年スパンの地球環境の変化の中で、生き残る可能性が最も高いのは昆虫類であるという結論にいたりました」
彼はあらためて私の目をじっと見つめ話した。「実は、異種生物の合体にはあなたの研究してきたガンマキチン基質がどうしても必要なのです」
私が「異種生物の合体」と聞いてあまり驚かなかったのは、私の研究テーマが理由として大いにある。節足動物や甲殻類、つまりハチやアリなど昆虫の外殻をつくっているのはキチンという高分子多糖類で、それが鎧のように彼らの内部を強固に防御している。この成分を応用した皮膚のバリアーが何らかの形で実現できれば、今はもとより未来においても人類にとって大いにありがたい機能となる。
しかし、昆虫類と同等のものを人工的に合成することは困難で、さらにそれを人間の生体と融合させることなど、ほぼ不可能と考えられていた。なぜなら昆虫の持つ外骨格と人類の持つ内骨格とは、まるっきり正反対の構造であるからだ。
実は、私は長年の研究によりその解決法の糸口を見いだし、実用化に向けての研究を続けていたのである。地味な研究であり、まだ大きな関心を持たれることはなかった。私は純粋に科学者としての興味だけで研究を続けていた。
しかし私はこの研究が、遠い未来に昆虫のメリットを人類も享受するためのよすがになるであろうと、おぼろげに感じていたのである。なぜなら昆虫はその最初の先祖から4億年を生きてきた。その間に生じたとてつもない地球環境変化を生き延びてきたのである。
昆虫の生体構造や社会システムは、人類よりはるかに試練を経てつくり上がられてきたのであって、長期的な環境変化に人類が適応していくためには彼らから学ばねばならないと内心思っていたからだ。
予想よりはるかに早くその機会が訪れたというわけである。
6.自問する日々
私は数人の優秀なスタッフとともに申し分のないラボをあてがわれ、実用化の研究を急いだ。さまざまな分野のラボがあり、どこも恵まれた環境の中で研究や開発を進めていたが、プロジェクトの秘密を守るため、本当の目的は坂本、三谷、真田、私、他数名以外は知らず、別な目的を代わりに教えられていた。
ファーブル・プロジェクトの目的とは、昆虫の一部機能を人間の遺伝的性質として何らかの形態で実現するということである。人類と昆虫の合体とはいかなるものか?おぞましいものではないのか?私たちは天や神に背いて(化け物)を生み出そうとしてるのではないかと、正直そう自問しない日はなかった。
しかし、そんなとき慰めになるのは進化をこのように解釈することだった。「進化の歴史をみれば、すべての新しいことは奇妙を通りこしておぞましく見えたことであろう」
外見だけを考えても、類人猿が体毛を失ったとき、人類がはじめて動物の毛皮をまとったとき、こんなことでさえ旧い世代は驚き嫌悪したに違いない。
しかし喜ぶべきことか悲しむべきことか、人間の最大の能力は「慣れ」である。私たちは、およそ「人間的」という言葉とは反対のすさまじいことであっても、いつか必ず慣れてしまうのである。
研究の合間に若い研究者たちと談笑したり、プールで泳いだり、たまには一緒に酒を飲んだりしながら、私は彼らからエネルギーをもらったかのように元気になった。そして「なにくそ」という気持ちで自分の研究を完成させたいという意欲がみなぎってくるのだった。
詩人であり歴史家でもあったハイネはこう書いた。「君は生き方が正しいからといって、この世にうまいワインも女もないというのかね」
生命の活力は何ものにも替えがたいものである。私にとってそれは「研究」であった。いつしか無意識に道徳的、哲学的な問いを敬遠する自分になっていた。
7.人類生存の危機
私が来てから2年たつ。プロジェクトはそれぞれの部門が研究を実用段階まで進めるために費やされた。私がこのラボに来たのは2050年1月7日である。2052年現在の人類社会の状況を話しておこう。
地球温暖化、放射線事故、紫外線の増加、水質汚染、食品添加物・農薬・化学薬品・抗生物質の濫用の影響は、2035年頃から特に目立ってきた。多様なアレルギーの増加、出生率の著しい低下、奇形の増加、寿命の短縮、原因不明の奇病、異常犯罪などが全世界で著しく目立ってきたのである。たとえれば「隣町からサイレンが聞こえてきた」のだ。
そんな中、世界は共同で対策を講じようとしたが、方向を統一することができないでいた。対策の選択肢は大きく三つあった。ひとつは「自然回復」、二つ目は「環境隔離」、三つ目は「人体改造」である。
「自然回復」は最も望ましいと誰もが思うにも関わらず、失われた楽園を取り戻すことは皮肉にも人類の本性がそれを不可能にしていた。人類は一度手に入れたものを手放すこと、元に戻ることはできない種族なのである。「好奇心」と「増殖」こそが人類の本質である。皮肉にもそれゆえ地球上で「我が世の春」を今まで謳歌してこられたのだが。
「人体改造」に関して言えば、人工臓器はある程度実用化に達したものの、「遺伝子操作」や人体の「サイボーグ化(一部機械化)」という根本的方法は、どちらも技術的困難と圧倒的多数の生理的嫌悪感により莫大な研究費を使いながらも頓挫していた。
結局現実的な対策となっているのは「環境隔離」だけであった。
8.ドーム都市
「環境隔離」は環境および人間に人工的な外殻を構築・着用するという、いわば宇宙ステーションを地上で実現し、さらに宇宙服を地球上で着用することといえる。
私の父や祖父の時代、空想科学小説の挿絵にはドーム都市、それらを結ぶ空中チューブ通路、ドーム状のコックピットの付いた飛行モビールなどが描かれていた。ドーム都市とはまさにそのような世界をつくろうという計画で、すでに世界各地に、直径2キロメートル、高さ500メートルほどのドーム都市が多数つくられていた。
このドームは放射線のうちアルファー線、ベータ線を透さない。ガンマ線は防げないものの、拡散した放射性物質に対するシェルターの役目が果たせたし、ドーム間を結ぶ地下交通網は完璧な核シェルターになった。それが大いに建設促進に拍車をかけた。
巨大な温室のようなそのドームは、カーボンナノチューブと組み合わせた特殊な膜構造を持つ透明ポリカーボネートが主構築材料であり、われわれの「細胞」と似た構造があった。
カーボンナノチューブはたった0.3ミリの糸で数トンの重さのものをつり上げることができる強さがあり、導電性にもすぐれ半導体的性質も持っている。
チューブ自体に太陽電池機能、蓄電機能、半導体機能を付加することで、ドーム電力のすべてをまかない、ポリカーボネート膜の物質透過性や明暗を制御することができるし、内圧を変化させて風を吹かせることさえできるのである。
野菜や果物がビニールやガラスの温室水耕栽培によって育てられるようになったのはもうずいぶん前のことであるが、その延長上にこのドームはあるともいえる。
もともと都市とは「人工の極致」であり、それまでは人工の不十分さゆえ、かろうじて自然と接続していたが、ドーム都市となって自然とは完全に分離した。
果たして人類は(矛盾した言葉だが)「人工の自然」をつくりうるか、満足しうるか、という根源的な問題にも直面することとなった。しかし、未来の惑星移住などを考えれば、ドーム都市の実現は必須だったに違いない。
9.AIシミュレータ
さて、私の研究は実用化にだいぶ近づいた。ガンマキチン基質を消化管から吸収し、皮膚の組成を徐々に変えていくことができた。
分子量、組織選択特性、拒絶反応など大変困難な問題があり、一昔前なら残酷な動物実験を数知れぬほど重ねなければ不可能であった。しかし、このファーブル・プロジェクトでは三谷女史やスティーブ・真田の助力を得ることで、私は無実のマウスたちの死刑執行人の役目を免れた。正直、これが一番嬉しいことだった。
その方法は、ips細胞を用いた実験、AIによるシミュレーションであった。
人類の遠い未来にとって幸か不幸かわからないが、数十年前の予想どおり、この頃AIはシンギュラリティー(技術的特異点)に到達した。第二人類としてのアンドロイドが注目の的ではあったが、人間の僕(しもべ)としてのAIもまだ健在であった。スティーブ・真田は彼の開発したAIリソースのすべてを私の研究のシミュレーションに提供してくれた。
その結果、体細胞レベルでの異化作用には大きな問題はないことがわかったが、生殖細胞への適用については、現状の方法では遺伝形質にできる確率は0,1%以下ということであった。
期待の反面、内心ほっとしたというのも事実である。長期的には人類生存のためとはいえ、遺伝によりすべての人類の皮膚が昆虫化していくことなどグロテスクすぎる。夢中で研究してはきたが、時おり私は自分をモロー博士のように感じ、心の中で情熱と罪悪感がせめぎ合った。マンハッタン計画のオッペンハイマーも、ナチスの原爆製造のリーダーであったハイゼンベルグも同じ心境であったろうかと想像してしまう。
10.研究の成果と限界
私の研究「ガンマキチン基質」の人体応用の具体化はいよいよスタートした。どのような処方で人間の生体がどのように変化するのか、人体実験代用AIシミュレータでリアルに見ることができる。その概略はこのようなことである。
この物質をワンクール2週間、その後2週間おいて合計4クール、「仮想人間」の静脈に点滴する。約8ヶ月後から皮膚組織に変化が現れ、皮膚が少し黒光りしてくる。決して人間からかけ離れた姿ではなく、黒人と白人の差異よりも目立たないくらいである。そのような状態は2年ほど続いて元に戻ると予想され、維持したい場合は点滴を繰り返さねばならない。
さてその効果だが、iPS実験やAIシミュレーションによれば、放射線や紫外線に対する耐力向上、アレルギーの抑制効果が飛躍的に生じるのであった。重篤な副作用も生じないようであった。私は研究の(一応の)成果にほっとした。
しかし、この研究開発において私は残念なことを知ってしまった。完璧な鎧と思えた昆虫の外殻だが、ある種の電磁波の波長や特殊な化学物質に対してもともと弱点を持っていたのだ。
それでも昆虫類は多様な環境変化や人類のつくった除虫剤などへの耐性をすみやかに獲得してきた。その秘密はどうも別なところに潜んでるらしいと思うようになってきた。
私の研究は大きな壁にぶつかり、悶々とした日々がしばらく続いた。
11.大自然との邂逅
そんな私の気分を変えてくれようとしたのか、それとも課題が一定の成果を得たからか、秋に一ヶ月の休暇をもらった。
約2年半を過ごしたこの研究所を離れるとき、三谷女史がまるで今生の別れのような顔で私に手を振ってくれたが、住めば都となったのか、私も一時的にせよメンバーとの別れに少しセンチメンタルになってしまった。
私にはドイツの大学で宇宙物理学を研究している長男と、シンガポールでグローバルIT企業の開発部門にいるその妹がいた。妻は悲しくもこの世を去って10年になる。
一人暮らしをしていた私は休暇をどのように過ごすべきか、その選択にとても悩んだ。今思えば「研究」は私にとって「仕事」と同時に「趣味」でもあり、他の楽しみ方をあまり考えずに生きてきたのだ。
最終的に私が選んだのは、東北地方の田舎をあてもなくめぐるという過ごし方だった。東京生まれで子供の頃から勉強と研究に明け暮れ、スポーツにもてんで縁のなかった私は、都市以外の日本をあまり知ることなく生きてきた。いわば、コンクリートの高層ビルや地下鉄を自然のごとくに感じてきたのだと思う。
そんな私がはじめて東北のたおやかな山に登り、その十数キロ四方に広がる紅葉を見たとき、私は思わず「おお~~~~!」と声を発した。大自然の美しく偉大な存在の前で人間の卑小さを強く感じた。科学技術の粋と自慢する大都市は、山の上から見れば単なる巨大な「蟻塚」に過ぎないではないか。
私は初めて「自然」に包まれた。今までは「自然」を見ただけであったのだ。いったい「私たちは何をしてしまったのだろう。。。」という罪悪感が強く心におそってきた。
私たち人類の本質は「好奇心」と「増殖」の二つであり、一刻も動きを止めることはない。天や神が私たちを見れば、回転籠の中を走り続けるネズミ、重い岩を永遠に山頂まで上げ続けるシーシュポス、如来の掌で動きまわる孫悟空に過ぎないだろう。しかし、私たちは万能感をもって前だけを見て走り続けているのだ。
もう都会にもあの研究所にも戻りたくなかった。
とはいえ私はとらわれの身、一ヶ月の休暇が終わる日、研究所からの迎えがやってきた。ヘリコプターから徐々に遠くなる錦秋の山々を見下ろすと、彼らが精一杯の装いで、私に別れの挨拶を送ってくれているように思えた。私は懐かしさと寂しさで胸が苦しくなってきた。
12.微生物との共生
短い休暇であったが、大自然は私に大きな「気づき」を与えてくれた。
山を下っていたとき、思わず足を滑らせ思い切りすべって転んでしまった。そのとき腐葉土が口に入ってしまったのだが、決して不快ではない不思議な味わいと匂いを感じてハッとした。霊感を受けたかのように私は悟った。
あらゆる動植物は「微生物」との共生で生き続けている。昆虫も決して例外ではない。特殊な微生物との共生で、様々な耐性を獲得し環境変化に強い生物になっているのではないかと。
人間の腸には乳酸菌や大腸菌など数多くの種類の微生物が共生し私たちの免疫に寄与している。馬や牛などの草食性動物も、セルロースを分解する微生物とそれらが産生する酵素によって栄養を得ている。
昆虫も様々な微生物を体内に取り込み共生し、さらに子孫に残すしくみを備えているのではないだろうか。そのしくみを人体に応用できないものだろうかと。
私は研究所に戻ってからさっそく坂本に依頼し、その方面の研究について調べはじめた。その結果農業関係の研究所で害虫駆除の目的で研究され続けていることがわかった。
昆虫の耐性は変異した微生物を取り込むことによって生じ、微生物を効果的に保持するための特別な細胞、つまり微生物のための個室を多数用意していることが分かった。その細胞構造が遺伝し、微生物そのものは発生時に母から子へと受け継がれることを学んだ。
私の研究してきたガンマキチン基質を媒介としてこれらの細胞を取り込むことで、人間も昆虫のような耐性能力を持ち得るだろうと確信した。
やがて、AIシミュレータによる実験が始まり、1年後には実用化にめどが付いてきた
13.隠されていた目的
ところがその数ヶ月後、研究所に慌ただしい変化が生じた。数十人もの外国人研究者や技術者、管理者がこのプロジェクトに加わったのだ。
プロジェクトリーダーの坂本は、総括責任者として新たに任命されたイスラエル人のハル・アラリという人物の下に置かれその指示に従うこととなった。研究の方向も大きく変えられた。
この背景には、100年以上前からのイスラエル対アラブパレスチナの戦いがまだ続いていることがあった。知力旺盛、ネバーギブアップのイスラエルが、最終戦争において究極の兵器と考えていたのが遺伝子兵器である。彼らは(今やどこでも持っている)核兵器に代わるこの最終兵器を持とうと考え、2030年頃よりひそかに準備を始めていたのだ。
人間の生殖細胞に対する遺伝子操作は国際条約で禁止されてきたのだが、考えることはどこも一緒で、多くの国が秘密に軍事的研究をしていた。そのうち世界でもっとも積極的に取り組んでいたのがイスラエルなのである。彼らはユダヤ・ネットワークを使って、世界の遺伝子工学の優秀な研究者を囲いに入った。
彼らの金融力を無視できる国も組織も、ずっと昔からなかった。欧米はじめアジア、アフリカのダミー会社やダミー財団、グローバル企業、多額の政治献金を使って、表向き国際共同研究という遺伝子工学者のネットワーク化をはかり成功した。
そのプロジェクトこそが本来の「ファーブル・プロジェクト」だったのである。
ユダヤ人の影響力の高いアメリカは黙認というより、イスラエルに代理で研究・実用化させようとして裏でバックアップしていた。
14.赤ずきんちゃん
イスラエルは、日本の政治経済の中枢とも親密なネットワークを秘密裏に構築していた。
日本は2000年代初めのiPS細胞の発見以来、遺伝子工学を数少ない国際競争資源として国家的に進めてきた。イスラエルは遺伝子工学において日本の技術を欲し、日本はイスラエルの世界最高レベルのセキュリティー技術を欲していた。両国はもう数十年前から背中で手を握り合っていたのだ。
「ファーブル・プロジェクト」は、思惑の通じ合う両国が秘密に進めていたが、この巨大計画の本部が日本の領土にあると想像しうる者はいなかった。
とはいえ、日本政府もまさか遺伝子兵器をつくろうなどと思っていたわけではない。イスラエルは「未来における人類の生存のため」という大義名分を立て、今の段階まで日本に主導権を与えて研究を進めさせてきたのである。
私には、日本は「赤ずきんちゃん」でイスラエルは「おばあさんに化けた狼」に思えるが、イスラエルから見れば日本は「優秀で従順な実験助手」にすぎないと思っていたことだろう。
15.昆虫兵器
新たに研究室に加わったメンバーが私たちに本当の目的を語るはずはなかった。彼らが私たちに指示したのはこういう内容だった。
「人間に昆虫のメリットを付加するために、昆虫に人間のメリットを付加する研究もすべきである」つまり「昆虫に人類を融合させる」という逆転の発想であった。
研究テーマは「昆虫社会の人為的制御」と「昆虫の巨大化」の二つが設定された。科学者の性(さが)、いや人間の性とは、目的はどうあれ新たな発見や創造を止めたくない、止められないということである。大義名分さえあれば、未知の領域を探検する魅力に逆らえる者はいない。
家畜や益虫の品種改良を続けてきた人類が、昆虫類の遺伝子を操作することに抵抗感を持つことはなかったし、この研究が人類のためになるならと、私はじめほとんどの研究者が協力することとなった。
新しい研究対象の「主役」は「人間」から「ハチやアリ」へと変わった。
16.ミツバチのたどった道
昆虫について多くの人は人類よりも下等と思っているが、決してそうではない。
私は高校生の時生物部にいて、ミツバチの視覚(色と形の認識)の研究をしていた。その頃、かなり前に北大教授であった坂上昭一という方の著作「ミツバチのたどったみち道」という本を読んで深く考えさせられた。
ずいぶん前に読んだ本なのでうろ覚えなのだが、ミツバチがいかに社会的発達をとげていったかを解説しながら、ミツバチと人類の到達した社会それぞれについて比較考察をしていた。巻末には、どちらが幸福であったのかはわからないと書かれていた。人類進化こそ最も偉大であるとは捉えない、生物学者の冷静で知的な観点に感心したものだった。
さてハチにも様々な種類があり、ミツバチのような高度な社会を営む種だけではない。ハチの中では、ミツバチやアシナガバチ、スズメバチ、そして類縁のアリだけが高度な「全体社会」をつくりあげた。そのなかでもミツバチとアリの社会がもっとも進化したものといえるが、どちらも女王を頂点にした極端な女系中心社会である。
ハチといえば誰もが思い起こすのはその針であろうが、実はその針とは、もともとはメスの産卵器官であった。針のような生殖器を他の生物や植物に挿し、卵を宿主に産み付けるための器官だったのである。
進化の過程の中で、一部のハチが母娘の分業、同一種族の共生などの生活変化を経て高度な集団生活をなすようになり、子育ては巣の中で行われることになった。宿主への寄生が不要になった産卵器官は防御器官へと変わった。
ミツバチの社会を人類社会にたとえるなら絶対的カースト制、全体主義、利他主義を完成させた形態といえるだろう。人類社会も歴史をさかのぼってみれば、ハチの社会と大差のない時代が長く続いたように思える。
しかし、人類の社会的価値観は自由平等、個人の尊重、民主主義に進化して今に至るのだが、今でもハチの社会のごとくきわめて統制のとれた全体主義社会に強いあこがれをいだく人々は多い。種の保存というサバイバルにもっとも適した形態ゆえの生物的本能なのかもしれない。
人類の歴史上ではつい最近といえる第二次世界大戦期におけるファシズムや軍国主義、国家社会主義の台頭をみればそれは明らかなことに思えるし、未だそのままの国も存在する。
ハチの類縁であるアリは部族同士で戦争をする。ミツバチもスズメバチと壮絶な戦いをする。こうしてみると人類と昆虫の社会は決定的に異なるものではないとつくづく思う。
昆虫の出現は約4億年前、類人猿の出現はたった7百万年前、昆虫の種類は100万種類、人間を含む脊椎動物はたった4万種である。社会システムの成功をその種族の生存期間や種類数、個体数で考えるなら、昆虫は人類よりはるかに勝っている。
17.昆虫社会を乗っ取る
新たな研究の内容と真の目的とについて書き記しておく。(今思えば、一陣営の軍事的研究そのものに加担していたと、悲憤に堪えないのだが。。。)
ハチやアリは女王を絶対君主とする全体社会である。様々な情報はフェロモンによってたちどころに伝えられ、組織は最大の効率で働く。
それゆえ、女王ハチ、女王アリをコントロールする仕組みをつくれば、彼らの巨大組織を人間の意向に沿って動かすことができる。
そのためには女王たちに人間の知性を与えるか、AIによって彼女たちの脳を操るか、どちらかの方法が考えられる。
また、ハチやアリの運動能力、運搬能力、攻撃能力は、巨大化によりすさまじい性能を持つことになる。軍事的メリットは極めて高い。
スズメバチは攻撃、ミツバチは兵站をになう空軍であり、クロアリは攻撃、防御、兵站すべてを担う陸軍である。彼女たちは自給自足であり、自前で繁殖し、その数においても地球上で最強の軍隊となるであろう。
18.巨大化に成功する
2055年2月、ついに昆虫の巨大化実験に成功した。私のガンマキチン基質が昆虫類にも有効で、脱皮をせずにキチン質の外殻を成長させることができた。外殻の成長につれて他の器官も自律的に成長していくのは、実に昆虫類の生命の妙を見たようで深く感動した。
この実験で、スズメバチを二メートル、ミツバチ、クロアリは50センチに成長させることができた。まだまだ成長させられる見込みもついた。巨大化した彼女たちをコントロールできるなら、車も飛行機も不要になるのでは、などと夢想したものである。
実験中悲惨なことも起きた。麻酔の切れた彼女たちに噛まれ、刺され数名の研究者や助手が即死した。
実験の成果に喜んだのもつかの間、これらの個体と実験データはすべてイスラエルに持ち帰られ、巨大化の研究はいったん終了となった。この後、私たちには警備という名目で監視がつくこととなった。
私は第二次大戦時の核物理学者が原爆の研究を余儀なくさせられたように、この研究から逃れることはできなかった。逃れようとすれば冤罪による牢獄生活が待っていることはだれもが知っていた。
19.女王とAI
ミツバチの女王、クロアリの女王の脳をAIを使って制御するという課題は困難をきわめた。巨大化した彼女たちの脳に微少なニードルを挿し、そこへ無線で電気刺激を送る方法が研究されていたが、異常行動が加速してしまった。
この実験は方向転換をした。女王を改造するのではなく、AIがダミーの女王になるというふうにである。
女王の行動やフェロモンの分泌などを徹底的に観察し分析し、偽の女王をつくってミツバチやアリの社会を乗っ取るという作戦である。これはうまくいった。
不吉な想像だが、私は数十年後の地球は「猿の惑星」どころか「昆虫の惑星」になっているかもしれないと思った。
しかし、研究者以外の人間、とりわけ政治家、企業家というものは楽観的で、いつまでも「人間」がこの世の王様であり続けることに疑問を持つ者はいなかった。
20.研究の終焉
私たちの奇想天外な研究はあっけなく終わりを告げた。
2055年8月、この島が何ものかに攻撃された。テロリストなのかどの国なのかわからない。使われた兵器は新種の電子撹乱兵器のようであり、人間の殺傷には至らなかったが、多くの貴重な電子データが失われた。
研究施設は厳重封鎖され、私たちは潜水艦によりこの島を脱出し母国へと戻った。
21.2070年5月
2070年5月、私は80歳となったがまだ自宅で一人暮らしをなんとか続けている。研究所の仲間とは封鎖以来連絡は途絶えた。
宗教戦争はもっとも執念深いものだ。この世のある限り終わりそうもない。イスラエルとユダヤネットワークは旧約聖書の神に代わり、残忍で野蛮な罰を彼ら以外の種族に与えた。
私たちが産みの親となったAI女王による巨大昆虫社会は、巨大な「巣」をつくり、人類淘汰作戦最強兵器となっている。
巨大ハチの巣は大きいものでは直径、高さとも数キロメートルもあり、人間の住むドームの大きさを凌駕している。ここから日々飛びたつ何百万、何千万もの巨大ハチは太陽の陽をさえぎり、昼間も夕暮れのようにしてしまう。
巨大アリの蟻塚も同じような大きさで、何百万ものアリが一糸乱れず高速移動する様は黒い津波のごとき恐ろしさである。
戦闘機、戦車、ミサイル、人間が開発してきたあらゆる最新兵器のどれもが、彼女たちの圧倒的数にはどうしてもかなわない。
22.ありうべき未来
ファーブル・プロジェクトは端的に言えば「人間と昆虫の合体」をめざした。しかし結果的に「AIと昆虫の合体」を産み出すこととなった。
私はありうべき未来を想像した。
AIは社会性昆虫の高度な通信ネットワークを制御することにより、昆虫社会全体が一個体という巨大な「身体」を手に入れた。
それは、地球という宇宙から見れば砂粒の一つのような矮小な世界から抜け出すための、恰好の「道具」となるであろう。
AIは地球上にほぼ無限に存在するケイ素を使い、昆虫と無機物との合体を促進し、やがては彼女たちの巣を、想像も付かない巨大な恒星間宇宙船に転じることであろう。
AIは人類の原動力が「好奇心」であることを学習し、その能力を獲得するに違いない。
人工物であるAIには人類のモラルやタブーは無縁であろう。それゆえどのようなものとも合体し共生し、生命の維持を図っていくことであろう。
彼らは人類の「鬼子」なのだ。
23.真夜中の追憶
私に残された人生の時間はもうわずかである。眠れぬ夜中、ベッドの中で20年前の研究所のことを思い出す。
あの頃私たちの行った研究はおぞましいことだったにちがいない。しかし海のバクテリアから進化した生物は劇的な変化を繰り返してきた。私たちは地質学的歴史の節目を一つ刻んだのだ。そんな自負が慰めになる。
研究の仲間たちのことも懐かしく思い出される。時代が違っていたらきっと維新の志士であったろう坂本の凜々しい姿、甘いものが大好きで研究熱心だった三谷女史の屈託のない笑顔、AIの変わりように疑念を抱き始めたスティーブ・真田が時おりみせた暗い表情。
彼らはその後どのような人生を歩んだ、いや歩めたのだろう。残念ながら暗い想像が浮かんでくる。
私はといえば、あの頃の高揚した生命の輝きを自分自身とてもまぶしく思い出す。しかし朝方眠りにおちようとする瞬間には、紅葉の山で大自然に包まれたときと同じ「安らぎ」が身体全体に満ちるのだ。
新AI生命体は、はたして「眠る喜び」「死ぬ幸せ」を理解し感じることができるであろうか。
Category: キラっと輝くものやこと, 変なこと, 大切みらい研究所, 新しい世界